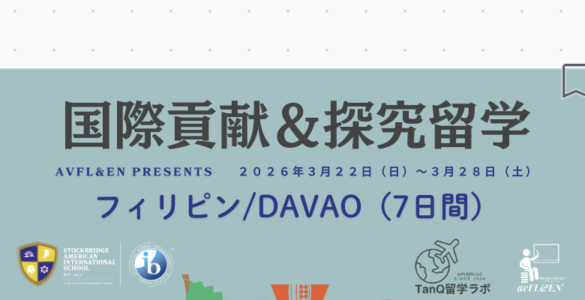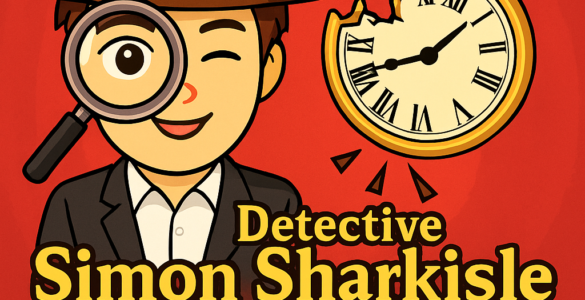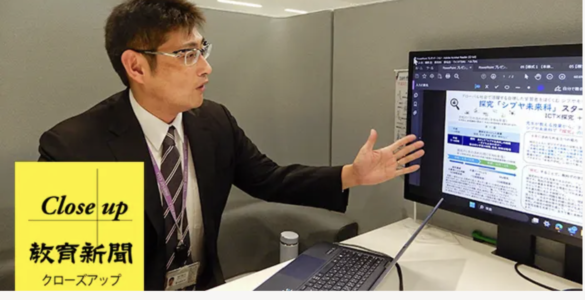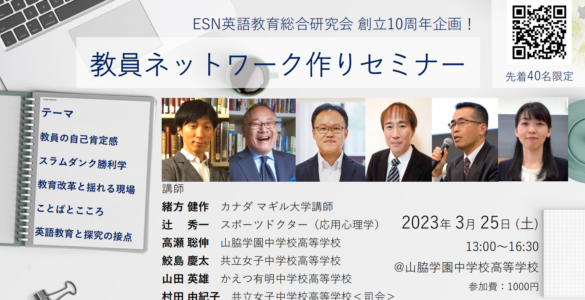山田進太郎D&I財団 石倉秀明様(COO)をお迎えして
2025年4月26日(土)に第19回目の女子教育研究会FENのオンライン学習会を実施しました。
登壇者は山田進太郎D&I財団 石倉秀明様(COO)です。
この財団は、メルカリ代表取締役の山田進太郎氏が2021年7月に設立し代表理事をされている財団です。D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)を推進することで、ジェンダー・人種・年齢・宗教などに関わらず、誰もが自身の能力を最大限に発揮できる社会の実現へ寄与することを目的としています。ジェンダー課題解決に向けた様々な取り組みや研究で知られています。
登壇者の石倉秀明氏はCOOとして財団の様々な活動を常任として積極的に運営されています。
2021年の財団設立当時17.9%であった女性のSTEM分野への大学進学率を2035年度には28%に引き上げることを目標にされています。
発表の冒頭では、まず日本のSTEM分野において女性が少ない問題について、様々な国際指標を用いて分かりやすくご説明頂きました。
・日本のSTEM分野への女子進学者の現状
→ 海外比較からの大きく引き離されている
→ ジェンダー課題を同様に抱えていると話題になる韓国にも大きく先を行かれている。
・PISAの成績:日本は優秀で男女差も小さい
→ PISAにおいて日本よりも男女差が大きい国(カナダ・フランス・ニュージーランド・スイス・オランダ・オーストラリアなど)で工学部への女性入学比率は日本より遥かに高い。
・九州大学 河野銀子先生の2025年の国内試験の分析では男女差がないことが明らかになっている。
・中学受験においても共学校では女子の方が合格最低点は高い学校が多い。
・Study Plusとの共同調査:中学生→男性が50%。女性は30%と理系に向いていると思う比率で差が出る
・STEM分野の女性人材登用について産業界は前向きだが増えない
→ 文理選択の段階で女子の理系選択者が少ない点が課題
・解決の具体策
→ ロールモデルとの対話
進路選択決定要因の理解:男子は数学などの相対的スコアで進路選択をする
理系クラスにおける男女比が女子に影響(環境に影響を受ける女子)に目を向けて課題として解決する
ジェンダーステレオタイプの強い異性の先生が数学を教えると女子はスコアが下がる→教育環境の課題
(ジェンダー課題に限らず、マジョリティがマイノリティを教えると悪い影響がある)
自信のなさ(保守的な選択):模試判定で志望校を下げる女子と下げない男子といった違いに注目する
同じ成績でも女子の方が理系科目に対して自信を持っていないことに配慮した支援が必要
女子は年内入試だと理系進路を選択しやすいことが分かっている。東大の推薦入試でも教育学部は全員女性、全体でも半分以上が女子。年内入試+女子枠というAffirmative Actionが有効。
・財団の事業
→ 奨学金女性事業とGirls Meet STEM(2024年6月にスタート)
石倉氏の説明は様々な研究データをベースに論理的に展開し、参加者の私たちも非常に分かりやすく課題を明確に捉えることができたと思います。
質疑応答では以下のような話題が出ました。
(Q) 石倉氏の発信に、「メルカリでは男性の3倍の時間をかけて打診しないと女性管理職になることを決断してくれない」とあったが、元共立女子中学高等学校の校長の前田先生はどうだったか?
→ 前田元校長からは、石倉様の発信の通り、リスク回避の心理と失敗したくないというプレッシャーを感じ、なかなかチャレンジしようという気になれなかった。また、すべてを自分で背負わなければならないという気持ちになり受援力に目を向ける余裕がなかったというコメントがありました。
この点については、石倉様の発信にもあったように、「女子比率が低い学部へのチャレンジを女子が躊躇する」ということと同様に、女性管理職が少数派であれば、ネガティヴなマインドはどうしても強化されてしまうのかも知れないと感じました。
こうした現状について、コアメンバーより、「女性活躍」を大々的に発信する記事に使われた3枚の写真が提供されました。G7における女性のEmpowermentの会合で日本だけが男性の大臣の出席であったり、神奈川県のWomen act.の中に12人の男性役員が並んでおり女性が1人もいない写真が使われたり、女子学生の増加を訴える国立10大学の理学部長が全員男性であったりという写真です。こうした構造を作り維持している権力者の退場といった変革がなければ、実情はなかなか変わらないのではないかという指摘がありました。
石倉様からは、「女性のみならずマイノリティが権利を獲得していく過程」について、まずマイノリティが権利獲得を実現した場合、歴史上一度もそれらが後退したことはないというFactが提示され、「なかなか変わらない」中で悲観的な解釈も当然生まれるが、時代の流れの中で必ず前進していくものだという強いメッセージがありました。
また、「社会規範・文化・バイアス」が先なのではなく、それらは結果であり、先にあるのは社会構造であること。つまり、産業構造・働き方こそがジェンダー課題となる社会規範や文化、バイアスを生むのだということを押さえておく必要がある、という話がありました。この点は非常に重要かつ鋭い本質的な視点で、私たちはどうしても「差別する人の心」を変えなければと考えてしまいがちです。しかし、それらを生む構造が変わらなければ、「心」は変わらないし、逆に構造が変われば「心」は変わるということです。製造業がまだまだ主産業である日本の場合、どうしてもマスキュリン(男性的)な働き方が優位になってしまう。ヨーロッパでなぜジェンダー課題の解決が進んだかと言えば、「製造業で負けたことにより知的労働にシフトしたことによって、働き方が変わり、家族の形も変わり、バイアスも変わってきた」という事実がある。ゆえに、「数が大事」であり、Affirmative Actionが必要だというお話がありました。また、このAffirmative Actionにより男性にもよい波及効果があったことについてもご紹介がありました。
石倉様のこの指摘、「製造業が衰退→産業構造の変化→知的労働へのシフト→社会構造の変化→意識レベルの変化→ジェンダー課題解決」という流れは、ノーベル経済学賞を受賞したゴールディンの分析とも符合するものだと感じました。
前回の登壇者の杉浦様も今回参加者側でご参加いただきました。芝浦工大へのインタビュー記事での取材から、高校受験段階で男女の学力差がないものが大学進学段階で大きな差になるのは、カリキュラムその他の教育現場に課題があるのではないか?女子に最適化した学びが実践されていないことや女子の進路指導を行う教員が、理系の進路に疎くなってしまうこともあるのではないかという指摘を頂きました。現場の教員としては耳の痛いご指摘ですが、元鴎友学園校長の吉野先生の過去のご発表でも、「女子校として女子に最適化された教授法やカリキュラムを追求してきた」というお話があり、杉浦様の指摘も現場としては真摯に受け止めなればならないものだと感じました。
ただ、私としては意外だったのですが、この点については、石倉様から「逆に女子に合わせた教育」に意識が行き過ぎることが原因であり、性差を過剰に考えすぎるのではなく、個人差として捉え、指導者・支援者のバイアスなどに留意し解決に向かうべきだという指摘がありました。確かに、イギリスの研究でも学習適性などにフォーカスし過ぎる教授では生徒の能力を伸ばせないといった研究結果が出されています。石倉様からは「教える側のバイアスが性差を作っている。囲碁でも男性が9割という世界で女子が男性に教わるとバイアスの影響を受けるが、AIで学ぶと影響を受けない」といったお話を頂きました。
続いて、「背中を押す」ということは重要だが、「阻害要因の除去」も必要ではないか、という声がコアメンバーから上がりました。石倉様からは、「参画→活躍→権利→新しい規範となり広がる」という4つのステップがあり、「黄金の3割」を達成することがスタートではないかというお話がありました。現実的には「リーン・イン」など、活躍する女性が男性化する課題などもあり、なかなか簡単に変化はしないのかも知れませんが、強引に構造を変えることが必要なのは間違いないと思います。
共学校の先生からは、「ジェンダー課題にフォーカスした発信は、男子生徒や保護者への配慮が必要だが、どのように配慮したらよいか?」といった質問も出ました。財団の活動では、そうしたケースでの配慮、工夫、説明などを丁寧に行っておられる現状があることをご説明頂きました。
「質的研究(定性)>量的研究(定量)」という特色を持つ大学で、定量的研究にチャレンジされてきた参加者からは、指導教官や周りの男子学生の支援により量的研究に取り組むことができたという報告もありました。バイアスに左右されない支援者の存在は石倉様のご指摘通り非常に重要な役割を果たすことを改めて感じました。
都市部ではない高校では、どうしても女子の進路が近所、現役進学に限定されてしまうような現状についての報告があり、この性差の課題も今後解決されるべき大きな課題ですね。
貴重な学びの機会を頂いた石倉様、質疑応答にご参加頂いた先生方、ありがとうございました。
この記事を書いた人
esn