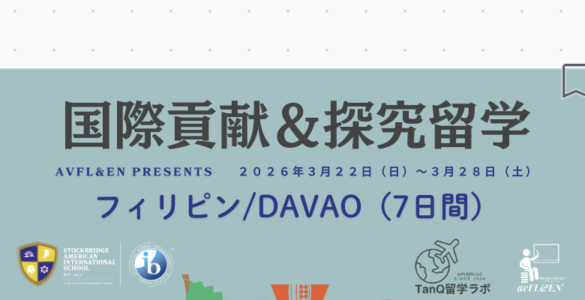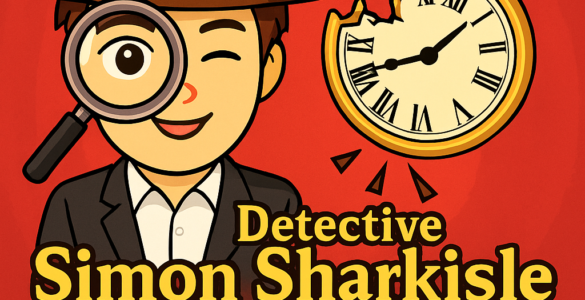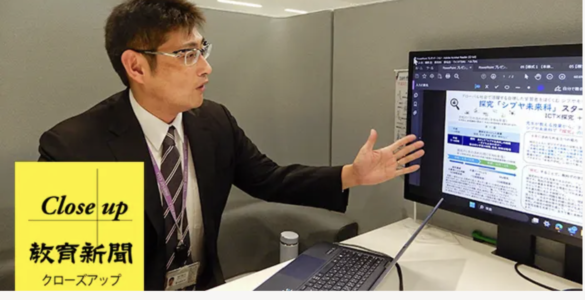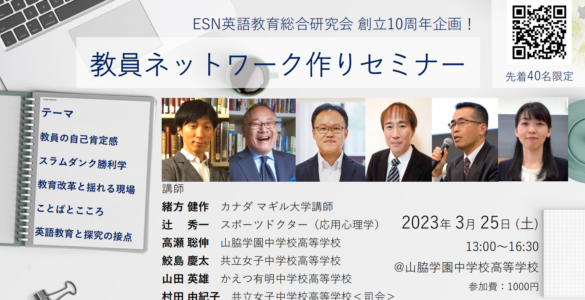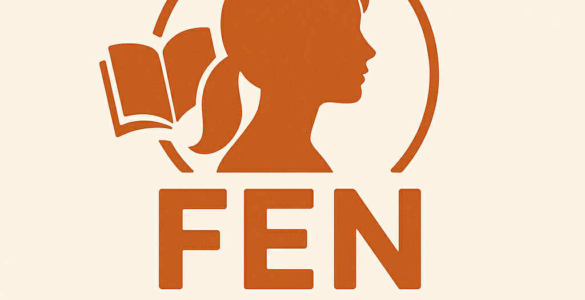小中学生の学力低下が話題になっています。
探究学習やグループワークが増え、基礎学習の時間が削られたことが原因ではないか、という指摘があります。
女子教育研究会にも登壇された杉浦由美子さんは、「探究・グループワーク重視が基礎学力と格差の拡大を招いている」 と論じました。
「学力低下」の原因はスマホでもコロナ禍でもない?法学者も指摘「小学校での探究やグループワークの増加」が問題か
この指摘は大筋で正しいと思います。
しかし、問題はもっと深いところにあると私は思います。
□ 探究が悪いのではない。引き算のない“理想の押し付け”が問題だ
探究は本来、子どもが自分の問いを持ち、世界とつながるための力を育てるものです。
しかし現場では、
基礎は当然できていること
自己肯定感が高いこと
協働できること
主体性があること
語彙力も表現力もあること
そして探究も深めること
という 「全部のせの理想の子ども像」 が前提になっているように思います。
それに対して現場の先生たちはこう感じています。
基礎をやれば「古い」と言われ、探究をやれば「学力低下」と言われる。
どちらに動いても、批判される。
これは、教員の力量不足ではありません。
探究を推進する人の理想主義が悪いわけでもありません。
□ 問題の出発点は、“大人の社会の都合”
2000年代以降、日本社会は、教育に対してこう言ってきました。
経団連・財界は、グローバル競争に勝てる人材を育てよ。データサイエンス人材も増やせ。
政治(特に内閣府・経産省) イノベーション・主体性・協働を教育に。ニューノーマルの教育を。
大学 政策決定の場に多くの大学人が関わりながら、主に入試を通じて、上記の財界や政治の価値観を学校へ下流に押し込む
つまり、大人の社会が抱える課題を、「教育に解決させようとしてきた」 のではないでしょうか?
しかし、そのとき 何を減らすか(引き算) は議論されませんでした。
結果としてどうなったか?
基礎は自力でできて当然。その上でグローバル人材も目指せ。
という過剰な要求だけが、すべての子どもに一律に積み上がった。
そしてその前提は、“踏み外したら戻れない社会”とセットだった。
日本は長らく、
良い大学 → 良い企業 → 安定
が“勝ち筋”である社会構造を維持してきました。
私が小学生の頃、1970年代には今ほど大学に行く人が偉い、金儲けをした人が偉いという価値観も今ほど浸透していたように思いません。
この構造の下では、
勉強で勝てる子 → 安全な人生
勉強で躓いた子 → 人手不足業務・低賃金労働
という 分断 が生まれます。
その象徴が、介護・保育・物流・清掃・医療補助などのエッセンシャルワーカーの過小評価 です。
社会を支えている仕事であるにもかかわらず、「代替可能な労働」として扱われ、報酬も待遇も十分に保障されていない。
移民を安く使おうといった発想が一部に見られるのも、こうした価値観が土台としてある社会だからなのだと思います。
“勉強で負けたら、代わりはいくらでもいる仕事へ”という構造が、教育の影の前提になっている。
この構造のまま「探究を」などと言っても、子どもは本当に自分の興味や関心にそった学びなどへ向かうことはないでしょう。
□ ではどう変えていけばよいか
ここで必要になるのが 、再三発信してきたフレキシキュリティ(高流動 ×高保障×リカレント・リスキリング) の思想です。
一度の受験で人生が決まらない社会
学び直しがいつでも可能な社会
仕事を変えても生活が損なわれない社会
エッセンシャルワーカーが社会の基盤として正当に評価される社会
これが実現して初めて、子どもたちは「今の受験競争」だけに人生を縛られなくなる。
つまり、
基礎学力は生活の土台として保障する
探究は「自分の興味で世界とつながる余白」として機能する
社会は「人生の複線性」を認める構造へ移行する
この三つが揃うことが必要です。
□ 教育は、社会の鏡である
学力低下や探究の是非は、教育だけの問題ではありません。
その背景には、
経済構造
雇用慣行
大学入試の役割
社会が人の価値をどう決めてきたか
といった 社会の深層の問題 が横たわっています。
子どもに押しつけられてきたのは、「未来への理想」ではなく、大人が解決できなかった課題そのものだったのではないでしょうか?
だからこそ今、問うべきはこういうことだと思います。
どんな社会なら、子どもが「自分の人生」を生きられるのか。
教育改革は、社会のあり方の更新とセットでなければ成立しないと思います。
教育の問題を学校の問題や教員の在り方に矮小化すれば、恐らくこの国は今後も疲弊を積み上げて、それこそ教育も社会も崩壊していくことになるでしょう。
学びが足らないのも、課題解決に取り組んでいないのも、私たち大人の方だという意識を持つこと、課題を下流に下流にと流していかないことこそが必要なのだと思います。
私自身がやれていることは、偉そうなことを言えるほどのことではありません。
フレキシキュリティにしても、リカレントやリスキリングが必ずしも上手くいかない他国の現状も知っています。
でも、日本の教育力って、そんなに悲観的になるほどの酷いものではないはず。リカレントやリスキリングについても日本が本気でやれば変わると私は信じています。
いかに勝つか?そのためにいかに努力をすべきか?牧歌的な教師気取り人たちへの否定も含めて、教育現場で私がやってきたことは現状の社会を前提とした構造の再生産だったと思います。
私の考えが根本的に変わったのは、定員の厳格化による入試ハードルの変動や年内入試へのシフトなどの変化もありますが、息子ができたことが大きなキッカケなのかも知れません。
自分の子どもだけを勝たせようとすれば、みんなが不幸になる。
ロールズの無知のヴェール。
この国に生まれた全ての子ども達が、どんな時代になっても幸せを創っていける
それこそが No one will be left behind. の本当の意味なのではないでしょうか?