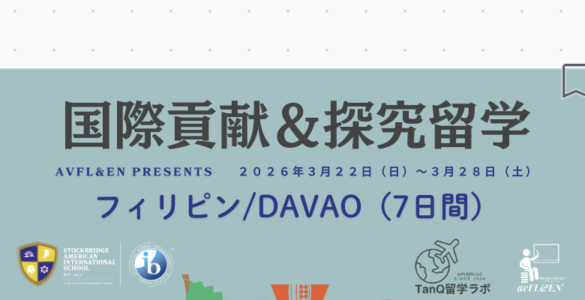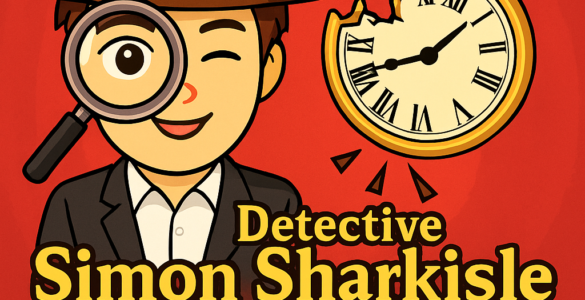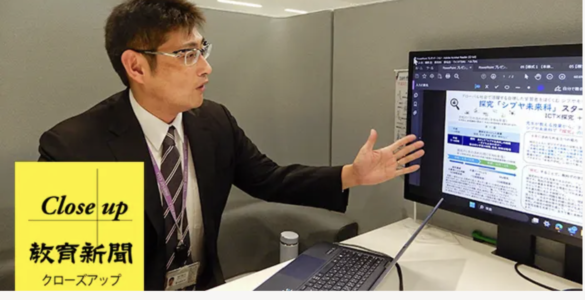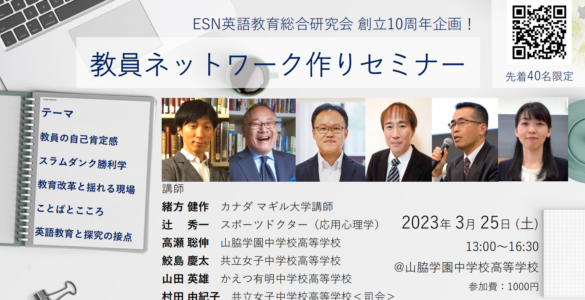登壇者 杉浦由美子氏 ノンフィクションライター
対談 前田好子 共立女子中学高等学校長・女子教育研究会FEN代表
このイベントの内容はメディア取材の依頼がございますので、今回は概略と私の個人的な感想を記録させて頂きます。
対談は、杉浦様が前田先生の中学から大学までの女子教育の経験と教員として母校に戻ってからの生徒の様子などをインタビューする形で進行しました。
内容は、「女子校あるある」の数々のエピソード、生徒たちの変化、生徒たちの現状など、経験に基づく具体的なお話でした。
これは私の主観的な感想になるのですが、こうしたインタビューは多くの場合、聞き手があらかじめ用意したストーリーのエビデンスとしての切り取りに着地したり
聞き手と話し手の変容がほとんど起こらない対話になりがちです。私自身もメディアの取材を受けたことがありますが、聞き手が記事として発信したいことが予め存在していて
話し手の発信したいこと、伝えておきたいことが、どこかで置き去りになってしまうことがよくありました。
今回の対話では驚くほどそれがなかった点がとても新鮮でした。
聞き手:最近の女子校では〇〇ということをよく聞くのですがどうですか?
話し手:確かにそれはあるかも知れませんね。でも〇〇は昔からあったものが少し変化しているという印象です。
聞き手:例えば、それはどのような時にお感じになりますか?
話し手:そうですね。例えば、文化祭の時に…
聞き手:そうなんですね。私の考えていたイメージと少し違いますね。ということは…
この会話のキャッチボールが、とても滑らかに、そして高速で行われていくのですが、お二人のコミュニケーション能力の高さだけでなく
・「知らないことは知ってるふりをしない」
・「分からないことは分かるふりをしない」
・「断言できないことは無理に言わない」
・「共有するバックグラウンドの違いを意識して、できるだけ分かりやすい言葉で相手に伝える」
という姿勢がお話を伺っていて本当に心地よかったですし、心からリスペクトできると感じました。
また、今回私が最も感動したのは以下のやり取りです。
杉浦氏:女子校出身者の様々な特質はどのような教育が生み出しているものだと思われますか?
前田氏:うまく言えませんが、「場」の力が大きいと思います。何かよくわからないけど、あの場で6年過ごすと皆それぞれ違うんだけど、共有して身についてしまうことがあるのではないでしょうか?
実際にはもう少し具体的な話もあったのですが、それは最近よく見られる以下の構図とは全く異質の発信でした。
「Aは、Bという教育の成果である。」
Bには具体的な教育プログラム、具体的な対策プログラム、具体的なICT活用、具体的な活動などが入ります。
こういう発信を聞く度に私は、「教育とはそんなに単純なものではない」といつも腹立たしく感じてきました。
そもそも、人間は個人差の大きな生き物だと思います。そこが他の動物とは違う。どちらかと言えば植物に近いのではないか?
実った成果は、この肥料がよかった、水がよかった、といった要素に還元できるものではなく、人間関係を含んだあらゆる要素で構成される「場」が育てるもの
何かが少しでも違ったらもしかしたら全体が崩れてしまうような、それでいて、要素の変化などではビクともしないそういう「場」こそが人を育てる、いや人が育つのではないか?
経験年数の長い教員(校内限定ではありません)が、「こうした生徒の成長は最近導入した〇〇プログラムの成果だ」と口にするのをなぜか最近よく耳にするのですが、その傲慢さだけでなく本質とかけ離れた発信に触れる度に、この人は教育現場にいて何を見て、何を感じてきたのだろうと悲しい気持ちになります。
対話の内容は「女子校あるある」として発信されましたが、ご参加頂いた方々の中には、別の女子校、共学校、インターナショナルスクール併設校などで勤務されている方もいらっしゃいましたので、質疑応答の時間に以下の点を確認することができました。
・「女子校あるある」と思われているものは共学校の女子にも見られる特徴や事象
・「女子校あるある」と思われているものは特定の女子校だけに見られる特徴や事象
・「女子校あるある」は多くの女子校に見られる特徴や事象
・「女子校あるある」は特定の時代だけに見られる特徴や事象
私の予想を超えて、「女子校あるある」は多くの女子校に見られる特徴や事象と感じられるものが多かったです。
もちろん、今回ご参加頂いた方々のサンプル数だけでは安易な結論は出せませんので、今回の対話を通して出てきた定性的な様々な事象は今後定量的な研究に繋げていかなければ、とも感じます。
特に日本では、こうした研究がまだまだ遅れているように感じます。
最後に、「一体今は何世紀なのかという疑問を感じてしまう日本社会の中で、今後別学や共学はどのような存在意義があるのか?」というお話になりました。
これについては、本研究会の伊藤先生が2023年の発達心理学会でも発信された通り、当面は「アジール的な女性専用車両のような存在意義」ということになるのではないでしょうか。
ただ、女子校に限らず、性別に限らず、子供たちの多様な個性にマッチングする環境がもっと広く議論され、研究され、そしてもっと多様な学校の存在を認める方向に私たちの社会が成熟していかなければならないのだと思います。「大した教育成果も出ていないような学校はつぶしてしまえばいい」という主張は、現場の教員は真摯に受け止めなければならない声ではありますが、ただ、そういう主張の中にある「教育成果」の質も当然問われるべきではないでしょうか?女子校の存在意義も、一人一人の子どもたちが成長するための多様な場の一つとして市民社会の中で理解・支持して頂けるように私たち現場の人間も学び続けていかなければならないという思いを改めて強く持たせてもらえるイベントだったと思います。